136号 SPRING 目次を見る
目 次
はじめに
乳歯う蝕は近年減少傾向にあるものの、増齢的に増加傾向が認められる。厚生労働省の歯科疾患実態調査(表1)によると、以前と比較してう蝕罹患率に低下がみられるが、増齢的にう蝕罹患率は上昇し、5歳では未だに60%以上の小児にう蝕がみられる。低年齢児のう蝕は減少しているが、口腔衛生状態が不良であれば、母乳の長期授乳や哺乳ビンの長期使用により重度の多数歯う蝕(ランパントカリエス)を生じる場合がある。
筆者の診療室は大学歯学部附属病院小児歯科専門の診療室であり、近隣の一般開業医から紹介され、重症う蝕児が多く来院している。
乳歯う蝕の臨床的特徴としては、同時に多数歯および多歯面にう蝕が発症すること、また、永久歯列ではう蝕感受性が低いとされている平滑面などから初発するう蝕が多いことである。さらに、う蝕が発症してから進行速度が速く、自覚症状が永久歯ほど明確ではないため、う蝕が重度になるまで見逃されてしまうこともある。
乳歯う蝕の好発部位は、咬合面、頰側あるいは舌側の小窩裂溝、隣接面歯頸部付近であるが、歯種や年齢により好発部位に違いがみられる。乳臼歯部については、3~4歳で咬合面小窩裂溝に、4~5歳で隣接面にう蝕が好発する。
乳歯う蝕を発症させないよう予防することが重要であるが、すでにう蝕を発症している場合は歯冠修復処置などの歯科治療が必要である。乳歯の歯冠修復の中で最も頻度の高い処置はコンポジットレジン修復であるが、歯髄処置を施した乳臼歯などは既製乳歯冠による修復が適応となる。
今回、筆者が日常臨床で行っている既製乳歯冠による修復法について解説する。
適応症
- 1. う蝕による歯冠の崩壊が著しい乳臼歯(図1)
- 2. 3面以上にう蝕のある乳臼歯
- 3. 生活断髄や感染根管処置などの歯髄処置を施した乳歯(将来歯冠の物理的性状の低下が予想され、歯冠破折などが生じる可能性が高くなる)
- 4. 半固定保隙装置(Crown loopやCrown distal shoe)の支台歯に応用する場合(図2、3)
- 5. 形成不全歯(エナメル質形成不全症など)
-
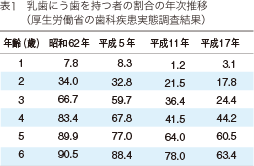
-

図1 歯冠崩壊が大きく歯髄処置の必要な乳臼歯。
-

図2 上顎左側に装着されたCrown loop保隙装置(乳歯冠は他社製品)(ミラー像)。
-

図3 下顎左側に装着されたCrown distal shoe保隙装置(乳歯冠は他社製品)(ミラー像)。
-

図4 表面麻酔剤を刺入点粘膜に塗布する。
-

図5 浸潤麻酔は根尖相当部の可動粘膜下に注入する。
-

図6 既製乳歯冠の形成に用いるダイヤモンドポイント。
-

図7 咬合面の削除を#330のダイヤモンドポイントを用いて行っている。
-

図8 咬合面の形成終了時(ミラー像)。
-

図9 隣接面の形成を#204のダイヤモンドポイントを用いて行っている。
-

図10 隣接面の形成終了時( の遠心面の形成はラバーダムを切ってしまう恐れがあるので最後に行う)(ミラー像)。
の遠心面の形成はラバーダムを切ってしまう恐れがあるので最後に行う)(ミラー像)。
-

図11 頰側面歯頸部の形成を#215のダイヤモンドポイントを用いて行っている。
術式
![]() にキッズクラウンを適応した症例を示す。
にキッズクラウンを適応した症例を示す。
1. 前準備
既製乳歯冠による修復を行う場合、局所麻酔を行うことが望ましい。歯髄処置歯であっても、歯冠形成時や乳歯冠の試適時に辺縁歯肉に対する刺激を小児が嫌がることが多いためである。ラバーダム防湿は全ての症例において必須である。
-
①局所麻酔
小児の歯冠修復のための局所麻酔は、通常浸潤麻酔で十分な効果が得られる。
浸潤麻酔に先立って、表面麻酔剤を刺入点粘膜に塗布する(図4)。表面麻酔の効果が十分現れてから浸潤麻酔を行う。浸潤麻酔は根尖相当部(乳歯の場合は歯肉頰移行部より固有歯肉に近い)の可動粘膜下に注入する(図5)。
小児の歯槽骨は成人ほど緻密ではなく、薬液が浸潤しやすいため、粘膜下注射で十分な麻酔効果を上げ得るので、疼痛を伴う骨膜下注射は避けるべきである。
-
②ラバーダム防湿
ラバーダム防湿は、歯冠修復処置のみならず小児の歯科治療時には必須である。ラバーダム防湿は治療時に小児が感じる不快感や恐れを抑制するのに役立ち、術野の明視化、口腔粘膜損傷などの事故防止といった利点がよく知られているが、その他の利点として、歯肉の圧排が挙げられる。既製乳歯冠修復の際には、ラバーダム防湿で圧排されて明視されている歯肉縁下の歯質を形成することにより、歯肉縁下約0.5mmの適切な形成が可能となる。
2. 歯冠形成
使用するバーは、#330(咬合面形成用)、#204・#215(軸面形成用)である(図6)。
-
①咬合面の形成
咬合面の形成には小円盤状ダイヤモンドポイント(#330)を用いる。咬合面の形態に沿って歯質を削除し、頰舌的に逆屋根状の形成とする。クリアランスは約1mmとする(図7、8)。
-
②隣接面の形成
尖状ダイヤモンドポイント(#204あるいは#215)を用いる。隣接歯を傷つける恐れがある場合は、直径の小さい#204を使用することが望ましい。隣接面には過度の傾斜をつけないように注意し、できるだけ歯軸に平行に形成する(図9、10)。
-
③頰舌側面の形成
頰舌側面も尖状ダイヤモンドポイント(#204あるいは#215)を用いる。歯頸部の豊隆部を歯軸に平行に削除し(図11)、咬合面側の斜面を少量削除することにより2面形成とする(図12)。
機能咬頭側(下顎は頰側、上顎は舌側)を2面形成することにより、乳歯冠の装着が可能となる。非機能咬頭側は強い2面形成とする必要はない。
軸面の歯頸部は歯肉縁下0.5mm程度(ラバーダム防湿で圧排されて明視されている部分を形成する)とし、歯軸と平行に形成し、鋳造冠とは異なりシャンファー型にならないよう注意する。
-
④各歯面の移行部を丸める
最後に、咬合面と軸面の移行部、隅角部を丸める(図13)。
3. キッズクラウン乳歯冠の選択と試適
キッズクラウン乳歯冠は上下左右第一乳臼歯と第二乳臼歯8歯種に、それぞれ#2~#7までの6種類の大きさの既製冠が用意されている。製造業者のコメントによると、キッズクラウンは弾力性のある硬さとシリカコーティング加工を施している点が特長である。
歯冠形成が終了したら、これらの中から形成歯冠の近遠心幅径にあった乳歯冠の大きさを選択する(本症例ではDEとも#2を選択)。ラバーダム防湿下に試適し、適合を確認する(図14)。乳歯冠を選択したら、ラバーダムを撤去し、対合歯とのクリアランスを確認する(図15)。その後、再度乳歯冠を試適する。試適時のチェックポイントは、形成が終了した歯冠との適合状態、乳歯冠の向きが歯列弓に一致しているか、隣接歯との接触状態、対合歯との咬合関係、そして辺縁歯肉との関係である(図16)。
乳歯冠の向きが歯列と一致していることを確認し、対合歯との咬合関係が適切であり咬合が高くないかを確認する。辺縁歯肉が圧迫され、白色(貧血帯)になっていないかを確認する。辺縁歯肉が白色を呈している場合は、乳歯冠の冠縁が長すぎるため、冠縁の調整を必要とする。
乳歯冠の適合度により、冠縁のクリンピング(内曲げ)を行う。クリンピングは通常ゴードンのプライヤーを用いる。強く内曲げをする必要があれば、バンドマージン(クリンピング)プライヤーを用いる場合もある。冠縁のクリンピングは1mm程度をプライヤーで軽くつまむようにして行う(図17)。乳歯冠を装着する際は、非機能咬頭側(上顎では頰側、下顎では舌側)をまず入れておき、機能咬頭側(上顎では舌側、下顎では頰側)へスナップを利かせてかぶせるように挿入する。最終的には、乳歯冠が歯面に接触しながらパチッと挿入できるように調整する。
-

図12 頰側面を2面形成している。 -

図13 咬合面と軸面の移行部を丸めている。
-

図14 ラバーダム防湿下でキッズクラウン乳歯冠を試適している。
-

図15 歯冠形成終了の咬合面観および頰側面観、対合歯とのクリアランスは1mm程度である(ミラー像)。
-

図16 乳歯冠を試適している(ミラー像)。
-

図17 冠縁のクリンピングを行っている。
-

図18 キッズクラウン乳歯冠の内部にセメントを満たし、まず徒手的に装着した後、割箸を用いてしっかりと適正位まで圧接している。
-

図19 冠縁から溢出したセメントを、ココアバターをつけた綿球でふき取り、デンタルフロスで隣接面の余剰なセメントを除去している。
-

図20 合着用セメントの硬化後、探針を用いて余剰なセメントを除去している。
-

図21 既製乳歯冠装着後の咬合面観(ミラー像)
-

図22 既製乳歯冠装着後の頰側面観(ミラー像)。
-

図23 上顎左側乳臼歯に装着された乳歯冠(他社製品)(ミラー像)。
4. キッズクラウン乳歯冠の合着
キッズクラウン乳歯冠を洗浄し、乾燥させる。乳歯冠の合着には、通常合着用グラスアイオノマーセメントを用いる。鋳造冠と異なり、既製乳歯冠の合着の場合は、形成が終了した歯冠との間に間隙がある可能性があり、合着用セメントは乳歯冠内面に満たすようにする。
歯冠を乾燥したまま、乳歯冠を装着し、割箸を用いてしっかりと適正位まで圧接する(図18)。
冠縁から溢出したセメントをココアバターをつけた綿球でふき取り、デンタルフロスで隣接面の余剰なセメントを除去する(図19)。
咬合をチェックし、患児に咬合させたままセメントの硬化を待つ。セメントが硬化したならば、探針とデンタルフロスを用いて余剰なセメントを確実に除去する(図20)。
既製乳歯冠装着後の咬合面観を図21に、頰側面観を図22に示す。また、他患の上顎に装着された既製乳歯冠を図23に示す。
おわりに
小児の歯科治療は迅速確実に行うことが必要であり、歯冠修復処置は一度の治療で完結させることが望ましい。また、乳歯の特徴を考えた治療法を選択する必要がある。乳歯の歯質は永久歯より薄く、歯質の硬度も低く、髄角が突出しているなどの特徴があり、乳歯の全部被覆冠の形成や使用する材料には配慮が必要である。すなわち、歯質の削除は少なくしなければならず、対合歯の咬耗を早めるような材料の使用は避けなければならない。
さらに、小児の歯列・咬合の発育を妨げないような配慮も必要である。このような観点から考えると、既製乳歯冠が乳臼歯の歯冠修復に用いられることは理にかなっている。
保護者が審美性を気にして既製乳歯冠の装着を嫌がることがあるが、乳歯が交換期まで正常に機能することを第一義とすべきである。
コンポジットレジン修復は審美性に優れるが、大きな窩洞に用いることは推奨されない。特に、う蝕が重度で歯髄処置を施した乳臼歯は元々残存歯質が少ないことが多く、将来歯冠の物理的な性状も低下することが予測され、歯冠破折などが生じる可能性が高いと考えられる。そのような症例で乳歯を交換期まで口腔内で機能させるためには、乳歯冠は有効な歯冠修復法であり、小児歯科に携わる歯科医師の皆さんに、本解説が参考となることを筆者は期待している。
同じテーマの記事を探す【 被覆冠成形品 】
モリタ友の会会員限定記事
- 176号 Clinical Report 幼若永久歯への既製冠の応用
- 164号 Clinical Report 装着時の誤飲・誤嚥を防ぎ、安全性を高めるキッズクラウンwithリング
- 164号 Trends 障害者(児)・高齢者のための新しい1-day 補綴治療
目 次
モリタ友の会会員限定記事
- Trends ノリタケデンタルスキャナーSC-3について
- 私の臨床 ノリタケカタナ&セラビアンZR「色の調和」と「天然歯らしさ」のバ「色の調和」と「天然歯らしさ」のバランス・カタナジルコニアフレーム臨床上の優位ポカタナジルコニアフレーム臨床上の優位ポイント
- Clinical Report クリアフィルR SAセメント オートミックス
- Clinical Report クリアフィル トライエスボンド NDを用いた接着性審美修復
- Clinical Report 既製乳歯冠による歯冠修復 -キッズクラウンを適応した症例-
- CLINICAL REPORT TBB系接着充填材「ボンドフィルSB」の臨床応用
- Trends 「ボンドフィルSB」について
- Clinical Hint 水流圧洗浄を利用した口腔バイオフィルムの除去効果
他の記事を探す
モリタ友の会
セミナー情報
会員登録した方のみ、
限定コンテンツ・サービスが無料で利用可能
オンラインカタログでの製品の価格チェックやすべての記事の閲覧、臨床や経営に役立つメールマガジンを受け取ることができます。
商品のモニター参加や、新製品・優良品のご提供、セミナー優待割引のある、もっとお得な有料会員サービスもあります。







