イメージアップ講座 一覧を見る
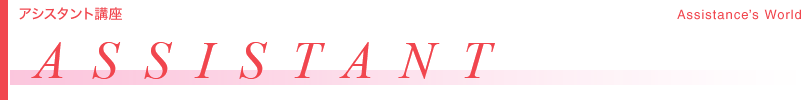
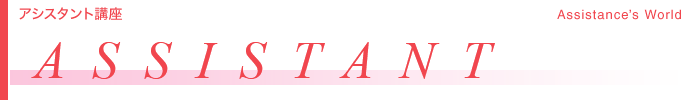
敬語を使えるようになりたい~パート1~
株式会社ロングアイランド 接遇マナーインストラクター伊藤 純子
前回は適材適所における言葉の使い分けの大切さについてお話ししましたね。今回は、敬語の役割とどんな種類があって、どう使い分けるのかという基礎知識、さらにどのように身に付けていけばよいかを、お伝えしたいと思います。
他の国の言語にも、丁寧な表現とごく親しい間で使う表現という区別はあるようですが、日本語のように、丁寧語・謙譲語・尊敬語がはっきりと分かれていて、それが今も現役で活用されているという言語は少ないようです。
ではまず、敬語の種類と効果、さらに使い方についてふれてみましょう。
◇敬語の種類と効果
敬語とは、話す相手や、話題に登場する第3者を立てて(敬って)表現したいときに用いる言葉です。
敬語には丁寧語・謙譲語・尊敬語の3種類があります。それぞれどんな役割があるのでしょう。
- 〇尊敬語・・・
- 相手および、その相手の動作や持ち物を表現するときに使う言葉です。尊敬語を使って、相手や相手の動作を表現することで、「私はあなたを立てていますよ」と言うことを伝える効果があります。『先生、今日は、何時にお出かけになりますか』というように、先生の“出かける”という動作を、尊敬語を使うことによって、先生を立てていることをあらわすことができます。
- 〇謙譲語・・・
- 自分のことや自分の身内のことを相手に伝えるときに使う言葉です。謙譲とは謙遜すると言う意味であり、謙譲語を使って、自分のこと、もしくは自分の関係者や身内のことを表現することで、相手をたてる、相手の立場を敬う効果があります。例えば、『院長の田中は外出いたしておりますので、戻り次第、ご連絡申しあげます』。これは、田中院長を院長の田中と呼び捨てにし、申しあげるという謙譲語を使って、身内である先生を謙遜した立場において、外部の方を敬った表現にするわけです。
- 〇丁寧語・・・
- 尊敬、謙譲、どちらの場合にも使う表現で、言葉の文末を《です》《ます》《ございます》としたり、名詞に“お”や“御”をつけて、丁寧で、上品な印象を表す効果があります(例えば、箸→お箸、茶碗→お茶碗、金→お金など)。ただし、電話番号、荷物、名刺、都合など、相手のものと自分もしくは身内のものをはっきりと区別させる時は、『お』は、尊敬語の意味もあります。患者様の電話番号は『お電話番号』ですが、自医院の電話番号には『お』は付けません。例えば、「〇〇様のお荷物です。私どもの荷物ではございません」「あいにく私の名刺は持ち合わせておりませんが、〇〇様のお名刺を頂けますでしょうか」というように、使い分けます。
おそらく、この3種類があることぐらいは、皆さんご存知だと思うのですが、誰に対して、誰のことを話すときに尊敬語を使うのか、謙譲語を使うのかという使い分けが分からない方が多いのではないでしょうか。
簡単にいうと、その状況において自分の立場を考えて欲しいのです。一番初歩の立場は、家族とそれ以外の方との関係です。家族は皆さんの身内であり、家族以外の方は外部の方という考え方です。つまり、外部の方と話すときは、身内の人間を下げて伝えることで、外部の方を敬っていることを表します。例えば、「父がよろしくと申しておりました。母はあいにく、出かけております」。
これを、皆さんの仕事に当てはめると、歯科医院で働く人はスタッフも院長も皆身内です。そして、患者様や業者の方、他の医院の方は外部の方になります。つまり、患者さんに対しては、「院長先生がまもなくいらっしゃいます」ではなく、「院長(の〇〇)はまもなく参ります」となります。
皆さんが年齢や立場の違う人と話すとき、これらの言葉を使わなければ、相手にしてもらえないことだってありますし、なにより、社会人として認められないでしょう。たとえ聞いてくれたとしても、不快感を持っているかもしれません。ましてや、仕事中の会話は医院の顔になるわけですから、医院の印象にも関わってくるのです。
当然必要なことはお分かりいただけますね。
◇敬語を身につけよう
では、敬語がまったく苦手な方が、敬語を身につけるにはどうしたらいいでしょうか。
「敬語の本を読む」。確かに、これも必要です。しかし、知っていることと使えることは違います。やはり、使い慣れることが一番です。
英語がいい例ですよね。いくら文法を知っていても、話せない人は多いのです。文法を知らなくても、外国に行って、必要に迫られて話しているうちに、話せるようになってくると言いますね。
●では、段階を追ってステップアップしましょう。
これから何回かに分けて、使い慣れていって頂きたいフレーズや言葉をお伝えします。まずは、手始めに、丁寧語からです。
言葉の終わり方を中途半端にせず、“です”“ます”をつけて、文章を語尾までしっかりと話すことを心がけましょう。
例えば、「あの―お名前は…」⇒「お名前を伺えますか」「どちら様ですか」。「こちらへ…」⇒「こちらへお入りください」というようにです。「なんだ」と思われるかもしれませんが、文章を途中で終わらせる話し方は、自信が無かったり、相手に頼っている心理の表れです。語尾の声が小さくなるのも同じことです。
まずは、しっかりと話すということが、相手を立てるという気持ちを伝えるうえで、無くてはならないことです。
焦らず、まずは、“です、ます”をつけて、しっかりと語尾まで、話すことから意識してください。これだけでも、丁寧さは伝わります。
ただ、それを伝える時、相手の目を見て話す、表情をつけて話すことは忘れないで下さい。「お手数ですが、こちらにご住所をご記入頂けますか?」という模範例が言えなくとも、笑顔で相手の目を見て、『こちらにご住所を書いてください』と言えば、決して感じが悪いとは思われません。
●さらに余裕のある方は
自分の電話番号は「私の電話番号」、相手の電話番号は「〇〇さんのお電話番号」、自分の荷物は「私の荷物」、相手の荷物は「〇〇さんのお荷物」というように、名詞の前につける《お》や《ご》のつけ方も意識してみてください。
と、今回は、ここまでです。
敬語は、“習うより慣れろ”です。日常生活や、仕事場で意識をして、少しでも多く使っていくことが、身に付く早道です。
次回は、『相手を気持ちよく動かす言い方』を練習してみましょう。

他の記事を探す
モリタ友の会
セミナー情報
会員登録した方のみ、
限定コンテンツ・サービスが無料で利用可能
オンラインカタログでの製品の価格チェックやすべての記事の閲覧、臨床や経営に役立つメールマガジンを受け取ることができます。
商品のモニター参加や、新製品・優良品のご提供、セミナー優待割引のある、もっとお得な有料会員サービスもあります。







